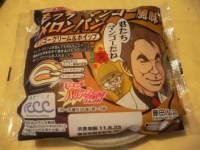私は医師(科学者の端くれ)ですので論理的・合理的なものが好きなんですね。
「寝技や談合、根回しが必要な政治」というのは好きではありません。
豪腕であるとか、影のナントカっていうのもキライです。
政治も透明性をもってやってもらいたい。
自民党の中にも、私の好きな議員はいます。
昔だと河野洋平、今だと河野太郎議員なんていうのは好きですね。
その河野太郎議員のブログに
原発の再稼働はできるか
というのがアップされています(6月14日)。
http://www.taro.org/
一部を引用すると
***引用
NHKの水野倫之解説委員や山崎淑行記者らは、最近出版された本の中で「先輩の記者には、『彼ら(電力業界)のいうことは信じるな』と指導されたものです」と述べている。
***引用終わり
彼らの言うことは信じるな、というのが
関係者の共通した感覚だろう、と書かれています。
あなたは電力会社の言うことを信じていましたか?
今でも信じていますか??
原発について電力会社は
ウソを言う、情報を隠す。
「安全だ」、と言い続けるしかなかったものだから、
事故を隠し
数値はねつ造し
労災事故の存在すら隠してしまった。
原発からの温排水の温度を、ずーっと1℃低く改ざんし続けていたことも
明らかになったそうです。
これまでの事故を洗いざらい全部出せ(公表しろ)
というだけでいいのです。
電力会社の言うことは信頼できない、ということがわかるでしょう。
しょっちゅう火災もおこっているし
しばしば放射線漏れ事故をおこしており
その通報が遅れたことを各地の知事などに何度も抗議されているのです。
中国新聞に
電力会社や原発メーカーなどでつくる社団法人日本原子力産業協会(東京)の参事の
方に取材した記事が出ています。
一生の仕事として原発を作り原発の安全性を社会に訴えてきた人ですが、
今は避難所で生活する立場となり、
さすがに
政府や東電の隠蔽(いんぺい)体質はもってのほか。
と語っておられます。
http://www.chugoku-np.co.jp/kikaku/fukushima/series/Fs201106210001.html
今すぐやるべきことは、情報の透明化だと強調する。「そうしないと人々の心は、原子力からどんどん離れていくばかりだ」
そのとおりだと思います。
まずは正しい情報を得て、正しい現状把握をおこなうこと。
原発の是非を判断・議論するのは それからでよいのです。
間違った情報をもとに原発を擁護する人がいます。
温暖化対策に原発推進、という人については
・原発は巨大な湯沸かし器です。
原発を冷やすために、温排水が大量に出ます。
その量は、太田川の流量の2倍。
その温度と量を計算してみてください。
(温度が低く改ざんされている可能性があるので注意。)
原発は、気温・水温を上げる装置なのです。
瀬戸内海のような閉鎖海域に多量の温排水を出し続ければとんでもないことになります。
原発はCO2を出さない、という人については
・原発を動かすために重油タービンを同時に回す必要があり
かならずCO2を出す仕組みになっています。
(最新鋭の1基だけは電気タービンなので違うそうです。)
原発はCO2を出さない、というのはウソです。
全国の原発で出るCO2は山梨県よりも多いそうです。
今回の原発震災のニュースのなかで
重油タンクも水没し、壊れている映像が流れました。
「なんで原発に大きな重油タンクがあるのか?」
と気づいた人がいたなら、いいセンスです。
原発を稼働するためには必ず重油を燃やす必要があるのです。
カープ チョッパー。
職業柄(?)チョッパーが好きですね。
背番号は 06。

★新型インフルエンザ情報
とくに新しい情報はありません。