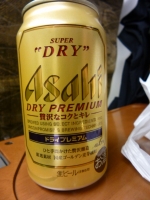コレステロールの高い人は、卵は?イカは?
昨日は暖かくなりましたね。
昨夜は21時すぎても土手を走っている人が何人もいました。
今日からまた寒くなるそうですから、気をつけましょう。
さて、
昨日の続きのような記事です。
コレステロールが高い、と言われている人も多いと思います。
食事療法、運動療法をしましょう、
ということになるわけです。
私たちは、「野菜類・海藻類をしっかり摂りましょう。運動しましょう」
というように指導します。
しかし、
コレステロールの多い食品を控えましょう、
と言われていた時期があって、
いまだにそれを言われる方がおられます。
いわく、
肉を食べないようにしています、
卵を控えています、
イカはコレステロール多いんですよね。
でも
私どもは、肉や卵やイカを控えるように言ったことは一度もありません。
同じ内容を上杉薬局さんが、
2月24日のブログにて紹介されています。
上杉薬局さん、ためになる記事が多いですね。
http://uesugi65.blog25.fc2.com/blog-entry-2752.html
***一部引用
コレステロールの食事制限必要なし
健康維持のために、コレステロールの取り過ぎに注意しましょう。
食事の改善を。
と、言われてきましたが、
先日、アメリカで
「コレステロールは過剰摂取を心配する栄養素ではない」
と公表されました。
各種調査結果から「食事によるコレステロール摂取と(動脈硬化などの病気の危険を増すこともある)血清コレステロールの間に明らかな関連性はない」と結論付けた。
***引用終わり
アメリカ発の記事、ということでニュースになりましたが
この内容は、アメリカだけではなく
日本の厚生労働省もすでに発表しております。
アメリカだけでなく日本でも同じことなんです。
コレステロールは人体(細胞)にとって必須の物質であって、
自分の体で必要な物は合成しているのです。
食事からの摂取が多ければ、合成を抑えますし、
食事からの摂取が少なければ、自分で合成を増やします。
食事でコレステロールを制限しても、あまり意味はありません。
以下、厚生労働省のホームページから
***
厚生労働省
「日本人の食事摂取基準(2015年版)策定検討会」 報告書
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000041824.html
脂質
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000042631.pdf
一部を引用します。
基本的事項
・コレステロールは体内で合成できる脂質
・経口摂取されるコレステロール(食事性コレステロール)は体内で作られるコレステロールの1/3~1/7 を占めるのに過ぎない。
・コレステロール摂取量が直接血中総コレステロール値に反映されるわけではない
・卵の摂取量と冠動脈疾患及び脳卒中罹患との関連は認められていない
・日本人を対象にしたコホート研究のNIPPON DATA80でも、卵の摂取量と虚血性心疾患や脳卒中による死亡率との関連はなく、1 日に卵を2 個以上摂取した群とほとんど摂取しない群との死亡率を比べても有意な差は認められていない。
卵の摂取量と冠動脈疾患罹患との関連を調べたJPHC 研究でも、卵の摂取量と冠動脈罹患との関連は認められていない。
また、糖尿病患者においても、卵の摂取量と冠動脈疾患罹患との関連は認められておらず、横断的な卵の摂取量と糖尿病有病率との関連も認められていない。
・コレステロールは動物性たんぱく質が多く含まれる食品に含まれるため、コレステロール摂取量を制限するとたんぱく質不足を生じ、特に高齢者において低栄養を生じる可能性があるので注意が必要である。
***引用終わり
今回は、
特に上記の最終段を知っていただきたいと思います。
「食べ力のある高齢者はお元気だ」
という実感は、誰しも持っておられると思います。
肉をしっかり食べている高齢者はお元気です。
高齢者こそ肉を食べろ、と言われるくらいです。
NHKクローズアップ現代 2013年11月12日
高齢者こそ肉を?!
~見過ごされる高齢者の“栄養失調”~
http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku/detail_3429.html
高齢者がコレステロール値を気にして
食事制限をするのは バカげたことです。
高齢者はカロリー不足、栄養不足になりやすいので
とにかくしっかり食べる、とくにタンパク補給をする、
ということを優先しましょう。
栄養が不足すると
筋肉量が保てず寝たきりになります。
(サルコペニア という単語で検索してみて下さい。)
じょくそう(床ずれ)が出来た場合には、
栄養状態を改善しないかぎり 治りません。
食べることが何よりの基本なのです。
逆に言えば
食べる力が衰えてきたら、そろそろ寿命 ということです。
それが自然の姿というものでしょう。
最近食べたパン
セブンイレブンのホットドッグ
新発売シールが貼ってあるけど、新発売なんでしょうかね?

★インフルエンザ情報
広島市では、注意報レベルを下回りました。
A型流行は一段落です。
あとは4月頃にB型流行があるかどうか、です。
広島県はホームページの更新が遅く、役に立ちません。