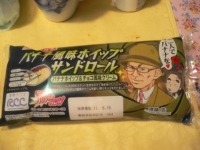ビワで唇が腫れる
19日の日曜日は、広島市医師会夜間急病センターで勤務でした。
夏なので患者数は少なかったです。
6月に入ってからもインフルエンザ検査は実施されていますが
陽性に出ている人はいませんでした。
ビワを食べて唇が腫れた、という人が来院されました。
ビワのアレルギーですね。
そこで終わってもいいのですが、
アレルギー専門医は、もう少し突っ込んで問診をします。
花粉症がないかどうか、がキーポイントですね。
花粉症はある、スギではない。
リンゴなどで唇が腫れたりノドの奥がかゆくなったりすることがある。
ということがわかりました。
これで診断がつきますね。
花粉症にともなう口腔アレルギー症候群 です。
花粉症患者さんのなかに、野菜や果物などでアレルギーをともなう人がいます。
唇が腫れる、ノドの奥がかゆい、
さらに重症だと嘔吐、息苦しさが出たりします。
花粉症の原因によって口腔アレルギー症候群が出やすい食品がわかっています。
たとえばスギ花粉症だとトマト。
リンゴや梨、ビワなどはバラ科植物という共通点があり
原因としてシラカバ花粉症が有名です。
シラカバは北海道や長野県が思い浮かびますね。
西日本にはシラカバが多いとは思えません。
では何が原因かというと、
西日本だと ヤシャブシ という植物が原因になるようです。
戦後にオオバヤシャブシを植樹したところ
花粉症+口腔アレルギー症候群が多発し、
六甲山などでは今では伐採がすすめられているそうです。
対策としては
疑わしい食品は避けること。
火を加えれば大丈夫であることも多いので
体調のよい時に少しだけ試してみる、というのはいいでしょう。
宮島には広島大学の自然植物実験所というのがあります。
通称は 広大植物園 と言います。
ですから、ときに観光客がタクシーで来て
「で、花を見せてください、花はどこですか?」
と言うことがあるのだそうです。
自然の状態にある植物を観察する場所ですので
お花畑のようなものは ここにはないのですね。
1~2時間で観察するコースがいくつも用意されています。
子ども会などで20~30名そろえば指導していただくこともできますよ。
先日、日本宇宙少年団広島分団で植物観察会をおこないました。
ヤシャブシが載っているかどうか、調べてみましょう。
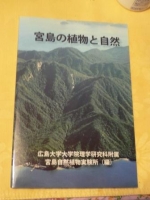
★新型インフルエンザ情報
とくに新しい情報はありません。